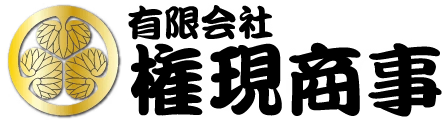一部改正 令和6年4月1日
第1章 総 則
目的
第1条この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2の規定に基づき、事業用自動車(以下「バス」という)の運行の安全管理及び事業遂行に必要な運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という)の指導監督についての職務ならびに必要な権限について定め、もって安全運行の確立を図ることを目的とする。
運行管理者等の選任
第2条 運行管理者(以下「管理者」という)の選任は、旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客運送事業の運行管理者資格者証を有する者の中から別表に定められた数以上の管理者を社長が任命する。
2 同一営業所に複数の管理者を選任する場合は、業務を全般的に統括する統括運行管理者(以下「統括管理者」という)を社長が任命する。
3 管理者の補助者(以下「補助者」という)を選任する場合は、運行管理者資格者証を有する者及び国土交通大臣が認定する基礎講習を修了した者の中から社長が任命する。
4 統括管理者、管理者及び補助者を選任、変更及び解任したときは、15日以内に営業所所在地を管轄する運輸支局長に届け出る。
5 選任した統括管理者、管理者及び補助者の氏名を社内の見易い箇所に掲示して全員に周知徹底する。
運行管理の組織
第3条 運行管理の組織は、次のとおりとする。
(1)管理者は、担当役員の指示により運行管理業務全般について処理する。
(2)統括管理者は、担当役員の指示その他により運行管理業務を統括する。
(3)統括管理者以外の管理者は、それぞれの職務分担を明確にしておくものとし、統括管理者の指示に従い、その業務を遂行する。
(4)補助者は、管理者の指示により運行管理業務の補助を行う。
(5)営業所と車庫が離れている場合は、管理者又は補助者が十分な管理を行える体制を講じる。
(6)管理者は、乗務員に対し、法令、社内規則及び管理者又は補助者の指示を忠実に遵守させ、輸送の安全確保に努めさせなければならない。
管理者及び補助者の勤務時間等
第4条 バスの運行中は、運行に関する状況の把握のための体制整備のため、少なくとも1人の運行管理者はバスの運転業務に従事してはならない。
管理者と補助者の勤務の関係
第5条 管理者は、職場を離れる場合又は補助者に補助させる場合には、補助者に業務の引き継ぎを行うとともに、補助者に対し補助させる職務の範囲とその執行方法を明確に指示し、かつ常に所在を明らかにしておかなければならない。
2 管理者は補助者の行った運行管理業務についても責任をもたなければならない。
3 補助者は管理者を補佐し、補助して行った業務について管理者に報告するとともに裁決を得なければならない。
第2章 権限及び職務
権限
第6条 統括管理者は、本規程に定める運行管理を統括する。
2 管理者には、本規程に定める職務を遂行するために必要な次の職務権限を与える。
①旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令、並びに運輸規則第36条の規定に基づく適格者以外の選任禁止に関する事項
②旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の要件を備えない者及び選任運転者以外の者の乗務禁止に関する事項
③酒気帯び運転者の乗務禁止に関する事項
④疾病、疲労、睡眠不足、麻薬等その他の理由により安全運転のできないおそれのある運転者及び車掌の乗務禁止に関する事項
⑤アルコール検知器の常時有効保持に関する事項
⑥運転者の過労防止、健康管理、労務管理に関する事項
⑦交替運転者の配置に関する事項に関すること
⑧乗務員のための休憩・睡眠又は仮眠に必要な施設の管理に関する事項
⑨乗務員の教育指導、監督及び特別な指導及び適性診断に関する事項
⑩運転者に対する、適性診断の受診に関する事項
⑪ 補助者に対する指導及び監督
⑫ 車両の配車及び乗務割当表の作成に関する事項
⑬乗務前・乗務後・乗務途中の点呼の実施並びに乗務事項に関する事項
⑭乗務記録に関する事項
⑮運行の主な経路の調査に関する事項
⑯ 運行指示書の作成及び運転者に対する指示に関する事項
⑰運行記録計に関する事項
(1)運行記録計の管理及びその記録の保存に関する事項
(2)運行記録計による記録のできない車両、その他整備不良車の運行禁止に関する事項
⑱車内の掲示(当該事業者の氏名及び名称、運転者名、車掌名、自動車登録番号)の取扱いに関する事項
⑲車両の非常ロ、車両の清潔保持に関する事項
⑳応急用具、故障時の停止表示器材及び非常信号用具並びに消火器の取扱い及び備付けに関すを事項
㉑苦情処理簿及び遺失物台帳に関する事項
㉒乗務員台帳の整備保管に関する事項
㉓運行を中断したときの措置決定に関する事項
㉔交通事故が発生した場合の措置並びに死傷者の応急措置の決定及び事故処理に関する事項
㉕自動車事故報告規則に基づく事故報告に関する事項
㉖事故の記録と原因究明及び事故防止対策と事故警報に基づく対策指導並びに事故統計に関する事項
㉗異常気象時における応急措置の決定及びこれに伴う運行指令に関する事項
㉘避難訓練等に関する事項、ただし、車庫、その他の施設及び運行中の車両火災の消火訓練、震災時の避難訓練等は統括安全衛生管理者又は安全管理者及び防火管理者と連携して行う事項
㉙その他、下記運行管理関係帳票類の記載と整理に関する事項
乗務員台帳、出勤簿、点呼記録簿、運行指示書、事故報告書、事故記録簿、事故統計、業務日誌、乗務記録、運行記録計による記録紙、苦情処理簿、遺失物台帳等
3 管理者は、安全運行の確保に関する必要な事項を上司に助言できる。上司は、管理者から助言があったときはこれを尊重する。
職務
第7条 管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則第48条及び本規程の定めに従い、誠実公正にその職務を遂行しなければならない。
選任運転者以外の運転禁止
第8条 管理者は、旅客の輸送を目的としない場合を除き、運転者として選任された者以外の者及び旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)の要件を備えない者にバスを運転させてはならない。
2 運輸規則第36条に定められた次の禁止事項に抵触しない者であること。
(1)日日雇い入れられる者
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(3)試みの使用期間中の者( 14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
(4)14日未満の期間ことに賃金の支払い(仮払い、前貸し、その他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)を受ける者
運転者の確保
第9条 管理者は、安全運行を確保するために必要な員数の運転者を常に確保するよう努める。
2 管理者は、運転者の採用に関して人事担当者に協力する。
乗務員台帳
第10条 管理者は、営業所に所属する運転者について、次の事項を記載した乗務員台帳(運転者台帳) を備え付け、運転者の実態の把握及び指導の際に活用する。
(1)作成番号及び作成年月日
(2)事業者名及び営業所名
(3)運転者の氏名、生年月ロ及び現住所
(4)雇入れ年月日及び運転者選任年月日
(5)運転免許証の番号、免許年月日、種類、条件及び有効期限
(6)運転経歴
(7)自動車事故歴(道路交通法第67条第2項及び自動車事故報告規則第2条に規定する事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合)
(8)健康状態
(9)特別教育の実施状況及び適性診断受診状況
(10)運転者の写真(作成前6ヶ月以内に撮影したもの)
2 運転者が転任、退職等により運転者でなくなった場合は、直ちに台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載のうえ、3年間保存する。
事故の記録
第11条 管理者は、事故が発生した場合には適切に処理するとともに、事故記録簿に次の事項を記録し、事故の再発防止を図り、運行管理上の問題点を把握し、その改善及び運転者の指導監督に資
(1)乗務員の氏名
(2)バスの自動車登録番号
(3)事故の発生日時
(4)事故の発生場所
(5)事故の当事者(乗務員を除く)の氏名
(6)事故の概要(損害の程度を含む)
(7)事故の原因
(8)再発防止対策
2 事故の記録は、当該営業所において3年間保存する。
乗務員の服務規律の徹底
第12条 管理者は、運行の安全及び服務について、乗務員に対し機会があるごとに内容の徹底を図る。
乗務員の指導監督
第13条 管理者は、運転者に対し、国土交通大臣告示「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年12月3日告示第1676号)により、バスの運転に関する事項について適切な指導監督をする。
2 管理者は、次に掲げる運転者に対し、前項の国土交通大臣告示の指針に基づき、特別な指導を行い、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせる。
(1)死者又は負傷者(自動車損害賠償補償法施行令第5条第2号「入院14日以上で医師の治療期間が30日以上の傷害」、第3号「入院14日以上の傷害」、第4号「医師の治療期間が1 1日以上の傷害」)が生じた事故を引き起こした運転者
(2)運転者として新たに雇い人れた者
(3)65歳以上の高齢運転者
3 管理者は、車掌に対し旅客自動車運送事業運輸規則第49条及び第51条に規定された事項について適切な指導監督をする。
4 管理者は、乗務員に対し非常信号用具、非常ロ及び消火器の使用取扱方法を指導する。
5 管理者は、自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、バスの運行の安全確保について従業員を指導監督する。
6 管理者は、前各号の指導監督を行ったときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を3年間保存する。
車掌の乗務
第14 条管理者は、車掌を乗務させなければならないバスに車掌を乗務させる。
点呼の実施
第15条 管理者は、品位と規律を保ち、厳正な点呼を行う。
2 勤務その他の事情により管理者が点呼を行うことができない場合は、指定された補助者が行う。
乗務前点呼
第16条 管理者又は補助者は、乗務を開始しようとする運転者に対し、安全運行を確保するため、次の各号により対面して乗務前の点呼を行う。
(1)原則として、個人別に行う。
(2)出発の30分程度前までに行う。
(3)営業所等の定められた場所で行う。
(4)日常点検結果に基づく運行の可否を確認する。
(5)酒気帯びの有無についてアルコール検知器を用いて確認する。
(6)運転者からその日の心身状況を聴取し、疾病、疲労、睡眠不足、飲酒その他安全な運転ができないおそれの有無について確認し、表情、姿勢等を観察して服務の適否を決定する。
(7)酒気を帯びていることが確認できた場合、又は健康状態が運転に不適切と認められ、又はその旨本人から申し出があった場合には、他の運転者に替えるなど適切な処置を講じ、その者を乗務させてはならない。
(8)運行する道路状況、天候、本人の勤務状況及び生活状況に照らして安全運行に必要な指示及び注意を行う。
(9)運転免許証、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書、その他業務上定められた帳西ンく、必要な携行品、金銭等の有無を確認するとともに、運行指示書、乗務記録、運行記録紙等の用紙を運転者に渡す。
(10)その他運行中、運行計画に変更が生じた場合等に報告させる事項を具体的に指示しておく。
2 管理者又は管理者は、点呼の実施結果について、点呼記録簿に次の事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引き継ぎを確実に行う。
(1)点呼執行者名及び点呼を受けた運転者の氏名
(2)点呼日時
(3)点呼の方法(アルコール検知器の使用の有無、及び対面、電話の別)
(4)運転者の酒気帯びの有無
(5)運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
(6)乗務するバスの自動車登録番号(又は社号)
(7)ロ常点検結果に基づく運行の可否の状況
(8)指示事項
(9)その他必要な事項
乗務後点呼
第17条 管理者又は補助者は、乗務を終了した運転者に対し、次の各号により対面して乗務後の点呼を行う。
(1) 帰着後速やかに行う
(2) 営業所等の定められた場所で行う。
(3)バス車両、道路及び運行状況について報告を受ける。
(4)酒気帯びの有無についてアルコール検知器を用いて確認する。
(5)安全運行を確保するために必要と認めた事項についての指示、注意の実施状況を確認する。
(6)乗務記録及び運行記録紙その他業務上定められた帳票、携行品、金銭等を提出させ、これを占検し収受する。
(7)原則としてロの勤務等について指示を与える。
(8)他の運転者と交替した場合は、交替運転者に対して行ったバス車両、道路及び運行状況の通告について報告を求める。
2 管理者又は補助者は、点呼の実施結果について、点呼記録簿に次の事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引き継ぎを確実に行う。
(1) 点呼執行者名及び点呼を受けた運転者の氏名
(2)点呼日時
(3)点呼の方法(アルコール検知器の使用の有無、及び対面、電話の別)
(4)乗務したバスの自動車登録番号(又は社号)
(5)バス車両、道路及び運行状況
(6)運転者の酒気帯びの有無
(7)交替運転者に対する通告
(8)その他必要な事項
3 管理者又は補助者は、乗務後の点呼の結果、運転者又は整備管理者に関係ある事項については、それぞれの関係者に通知又は適切な指示をし、特に異例な事項は上長に報告して確実に処理する。
行先地点呼
第18条 管理者又は補助者は、乗務の開始地又は終了地が営業所以外の地であるため、乗務前又は乗務後の点呼、報告及び指示を営業所で行えない場合は、電話その他の方法により行い、運転者の酒気帯びの有無の確認については、営業所に備える遠隔地対応型アルコール検知器を携行させて行う。
乗務途中点呼
第19条 管理者又は補助者は、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車に乗務する運転者に対し、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、次の事項について報告を求め確認を行い、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
(1)事業用自動車、道路及び運行の状況
(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転ができないおそれの有無
2 管理者は、点呼の実施結果について、次の事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引き継ぎを確実に行うこと。
(1)点呼執行者名及び点呼を受けた運転者の氏名
(2)点呼日時
(3)点呼の具体的方法(対面、電話の別)
(4)バス車両、道路及び運行の状況
(5)運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
(6)乗務するバスの自動車登録番号(又は社号)
(7)指示事項
(8)その他必要な事項
点呼記録の保存
第20条 管理者は、点呼の実施結果の記録を記載の日から3年間保存する。
アルコール検知器の有効保持
第21条 管理者は、営業所に備えるアルコール検知器を常時有効に保持する。
過労防止の措置
第22条 管理者は、常に乗務員の健康状態等を把握し、過労にならないようにするため、国土交通大臣告示(平成13年12月3日告示第1675号)による勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに基づきバスに乗務させる。
2 管理者は、乗務員の休憩、睡眠又は仮眠に必要な施設を適切に管理する。
3 管理者は、健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒、酒気帯び、覚せい剤の服用、異常な感情の高ぶり及び睡眠不足等により、安全な運転又はその補助をすることができない乗務員をバスに乗務させてはならない。
4 管理者は、運転者が長距離運転及び夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替する運転者を配置する。
5 管理者は、交替運転者を配置したときは、運転者に対して運転を交替する場所又は時間を具体的に指示する。
6 管理者は、乗務員に対して運行途中の休憩場所及び休憩時間を指示する。
7 管理者は、乗務員が事業用自動車の運転中疾病、疲労その他の理由により安全な運転を継続し、又はその補助を継続することができないおそれのあるときは、当該乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
運行経路調査
第23条 管理者は、運行の主な経路の道路及び交通状況を事前に調査し、 これに適すると認められるバスを運行させる。
運行指示書による指示
第24条 管理者は、運行ごとに次の事項を記載した運行指示書を作成し、 これにより運転者に対し適切な指示を行い、運転者に携行させる。
(1)乗務員の氏名
(2)運送契約の相手方の氏名又は名称
(3)運行の開始及び終了の地点と日時
(4)運行経路と主な経由地の発車到着日時
(5)旅客が乗車する区間
(6)運行に際して注意を要する箇所の位置
(7)乗務員の休憩地点と休憩日時(休憩がある場合に限る)
(8)乗務員の運転又は業務の交替の地点
(9)乗務員の宿泊先の名称と住所
(10)その他運行の安全を確保するために必要な事項
2 管理者は、運行の途中において、前項第3号から第10号に掲げる事項に変更が生じた場合は、運行について適切な指示を行い、運行指示書に変更の内容、理由及び指示をした管理者の氏名を記載させる。
3 管理者は、運行指示書を運行終了の日から3年間保存する。
乗務記録
第25条 管理者は、乗務前点呼時に運転者に対して、乗務記録の用紙を交付し、次の事項を記録させ、乗務後点呼時にこれを提出させる。
(1)乗務したバスの自動車登録番号(又は社号)
(2)乗務員の氏名
(3)乗務開始及び終了の地点と日時、主な経由地、乗務した距離
(4)旅客が乗車した区間
(5)乗務員の休憩地点と休憩日時
(6)運転交替及び車掌交替の地点と日時
(7)乗務員の宿泊先の名称と住所
(8)事故、路上故障又は著しい運行の遅延その他異常な状態の概要と原因
(9)車掌が乗務した場合はその車掌名
2 管理者は、前項の乗務記録の内容を検討し、運転者に対して必要な指導を行う。
3 管理者は、乗務記録を記録の日から3年間保存する。
運行記録計による記録
第26条 管理者は、乗務前点呼時に運転者に対して、運行記録計の記録用紙を交付し、乗務後点呼時に記録した用紙を提出させる。
2 管理者は、記録内容を検討し、運行の状況を把握するとともに、異常が認められる記録については、当該運転者に対して事情を聴取し、注意を与える等指導監督を行う。
3 管理者は、記録計の故障により記録できないバスを運行させてはならない。
4 管理者は、記録用紙を記録の日から3年間保存する。
5 運行記録計の具体的な取扱いについては、別に定める。
事故発生時の措置
第27 条管理者は、バスの運行中事故が発生した場合には、別に定める「事故処理要領」により対処する。
事故防止対策
第28条管理者は、事故防止対策を講じるために、次の事項を処理する。
(1)事故(軽微な事故を含む)については、その内容、原因等を記録して資料(カラー写真等)を整理しておく。
(2)道路、交通、事故状況等に関する情報(テレビ、ラジオ又はインターネットによる情報、事故統計、事故警報その他)を整理し、速やかに事故防止対策を講じる。
(3)管理者は、乗務員等に対して、自動車事故報告規則第5条の事故警報が発令された場合には、その警報による事故防止対策の措置を講じる。
異常気象時等の措置
第29条 管理者は、異常気象等により安全運行に支障が生ずる場合には、別に定める「異常気象時措置要領」により対処して運行の制限等を行い、旅客の安全確保に万全を期する。
非常信号用具等
第30条 管理者は、バスに赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具ならびに消火器を備え付ける。
2 管理者は、前項の備え付け品の検査を定期的に行わせて性能を確保する。
3 管理者は、運行中の火災及び震災等の非常の場合に備え、乗務員等に対して定期的に消火訓練及び避難誘導訓練を実施する。
車両の清潔保持
第31条 管理者は、バス車両を常に清潔に保持するよう指導監督し、定期的に車両の清掃状況を検分する。
シートベルトの着用等
第32条 管理者は、乗務員に対して道路交通法の規定に基づくシートベルトの着用を義務付け、装着を確認のうえ乗務させる。
2 管理者は、乗務員に対して乗客がシートベルトを確実に装着させて運転するよう指導する。
3 管理者は、乗務員に対して乗客がシートベルトを常に着用しやすい状態に保つよう指導する。
付則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から実施する。
付則(平成27年5月1ロ)
この規程は、平成2 7年5月1口から実施する。
付則(平成28年12月1日)
この規程は、平成28年12月1日から実施する。
付則(平成30年6月1日)
この規程は、平成30年6月1日から実施する。
付則(平成30年11月1日)
この規程は、平成30年11月1日から実施する。
付則(令和6年4月1日)
この規定は、令和6年4月1日から実施する。
別表運行管理者の必要選任数
| 事業用自動車の数 | 行呂理者数 |
| 39両まで | 2人 |
| 40両~ 59両 | 3人 |
| 60両~ 79両 | 4人 |
| 80両~ 99両 | 5人 |
| 100両~ 129両 | 6人 |
| 130両~ 159両 | 7人 |
| 160両~ 189両 | 8人 |
| 190両~ 219両 | 9人 |
栃木県バス協会